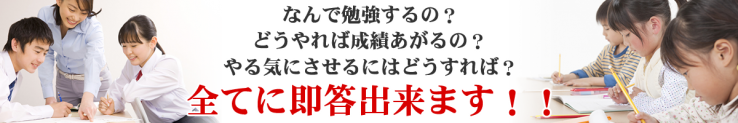
お知らせ
日本人の裁判観とアメリカ人の裁判観
こんにちは!!
s-Live東京つつじが丘校の宮岡です。
今日は、自分の好きな映画なのですが、
『12人の怒れる男』という映画です。
白黒の映画で、かなり古い作品ですが、自分にとっては名作の一つです。
この映画は、死刑と陪審員制度の話です。
一人のスラム街在住の黒人少年が、父親を刺殺した疑いで逮捕されます。
その判決を決める裁判では、あらゆる証拠が黒人少年を犯人だとほのめかしています。
また、当人のアリバイも証明できず、状況証拠的にどう考えても黒人少年が犯人で間違いないというところから始まります。
アメリカの陪審員制度では、全会一致が原則なので、一人でも死刑に反対する者がいれば、
再度話しなおしたため、陪審員の雰囲気としては、さっさと死刑で全会一致して帰ろうという雰囲気でした。
陪審員の一人である主人公は、犯人ではないということを主張するよりは、
「人間の命を奪うという決断を5分でするべきではない」という考えの下、一人だけ死刑に反対し、
陪審員たちと話し合っていきます。
もともと、証拠が状況証拠なうえに、
死刑賛成派の登場人物が固定観念や事件とは関係のないところでの印象などにより、
死刑に賛成した人たちばかりなので、主人公がいろいろと主張するうちに、
一人、また一人と死刑反対の側へ回っていき、
最終的には全会一致で死刑反対というところへ結論が持っていかれます。
現在、小中高の子どもが見ても、正直何が面白いのかはわからない映画だと思います。
もしかしたら、主人公が圧倒的に不利な状況をひっくり返すカタルシスを面白さだと解釈するかもしれません。
最も多いのは、「何でこの容疑者が犯人でないとわかるの?」という疑問だと思います。
個人的には、この映画の面白さは、時代や国を超えることで、
法・裁判・刑罰の解釈がここまで異なるものなのかということを感じられる部分にあると感じます。
法には「疑わしきは罰せず」という原則があります。
たとえば、
○○という事件を起こせる状況にあった人が容疑者とされたとしても、その容疑者は犯人とはいえない。
という原則です。
あくまで、凶器から犯人の指紋が検出された、現行犯だった、など、客観的な証拠がなければ、
犯人として、刑を執行することはできないということです。
そして、これについて映画の陪審員は熟知しており、おそらく公開当時のアメリカ社会でも一般的な考え方だったのでしょう。
そして「当たり前」であるがゆえに、映画の中では解説などもありません。
あくまで、登場人物たちの出した結論は、「犯人とするには証拠不十分。また調べなおしてね。」くらいのものなんですが、
映画のクライマックスの、登場人物たちの晴れやかな表情や演出から、
「冤罪を晴らしたのかな?」という印象を受け取ってしまいがちだと思います。
ではなぜ、彼らの出した結論はそこまで大げさなものではなかったのに、
登場人物たちは晴れやかな表情をしていたのでしょうか。
そこにも、アメリカ社会と日本社会の空気感の違いが表れているのです。
続きはまた次回で。







